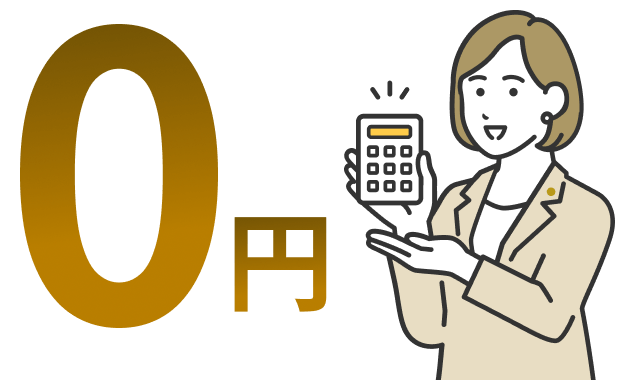遺産相続でまずやることは? 手続きの種類や流れを解説
- 遺産を受け取る方
- 相続
- まずやること

さいたま市が公表している「第22回さいたま市統計書」によると、浦和区における令和3年中の死亡者数は1298件でした。
家族が亡くなり相続が発生するとさまざまな手続きを行う必要がありますが、手続きのなかには、期限があるものも存在します。期限を超過してしまうとペナルティーが生じる可能性もあるため、必要な手続きをしっかりと把握して、スケジュールを立てながら適切に進行することが大切です。
本コラムでは、遺産相続の手続きの種類や流れについて、ベリーベスト法律事務所 浦和オフィスの弁護士が解説します。
1、相続が発生した直後にやるべきこと
相続が発生した直後にやるべき手続きとしては、以下のものがあります。
-
(1)死亡診断書の取得
被相続人が死亡した場合には、死亡を確認した医師から「死亡診断書」を発行してもらいましょう。
死亡診断書は後述する死亡届を取得するために必要な書類になるので、速やかに発行させるべきです。
なお、事故死であった場合には、「死体検案書」が発行されます。 -
(2)関係者への連絡
被相続人が亡くなったことを、家族、親族、友人、職場関係者などに連絡しましょう。
この段階で故人と付き合いのあった方全員に連絡することは難しいため、葬儀に来てほしい人たちに絞って連絡することが一般的です。 -
(3)葬儀の手配
家族が亡くなった場合には、できるだけ早く葬儀の手配を行いましょう。
葬儀会社に相談をすれば、お通夜や葬儀の日程についてアドバイスを受けることもできます。
2、7日(1週間)以内にやるべきこと
以下では、被相続人が亡くなったことを知ってから7日(1週間)以内にやるべき手続きを紹介します。
-
(1)死亡届の提出
家族が亡くなった場合には、市区町村役場に死亡届の提出が必要です。
提出先は、以下のいずれかの市区町村役場になります。- 被相続人が死亡した場所
- 被相続人の本籍地
- 届出人の住所地
死亡診断書は死亡届の用紙と一体になっているため、あらためて取得する必要はありません。ただし、死亡診断書以外の部分は遺族が記入する必要がある点に注意してください。
なお、葬儀会社に葬儀の手配を依頼した場合には、死亡届の提出は葬儀会社が行ってくれることが一般的です。 -
(2)火葬許可申請書の提出
遺体を火葬する場合には、火葬場に火葬許可証を提出する必要があります。
火葬許可証の申請については、法律上期限が定められているわけではありませんが、死亡届の提出と同時に火葬許可証の申請を行うことが一般的です。そのため、葬儀会社に依頼した場合には葬儀会社が申請もしてくれることが多いです。 -
(3)健康保険の資格喪失手続き
亡くなった方が会社員で健康保険に加入していた場合には、健康保険の資格喪失手続きが必要になります。
資格喪失手続きは、故人の勤務先の担当者が行うため、早めに連絡するようにしましょう。
なお、健康保険の資格喪失手続きの期限は、原則として死亡日から5日以内とされています。
3、14日(2週間)以内にやるべきこと
以下では、被相続人が亡くなってから14日(2週間)以内にやるべき手続きを紹介します。
-
(1)年金の受給停止
亡くなった方が年金の受給をしていた場合には受給停止の手続きが必要になります。
過剰に年金を受け取ってしまうと、後日返金の返還手続きが必要になるため、早めに手続きを行いましょう。
なお、手続きの期限は、国民年金の場合は死亡日から14日以内、厚生年金の場合は死亡日から10日以内とされており、年金の種類によって期限が異なることに注意してください。 -
(2)世帯主変更届の提出
亡くなった方が世帯主であった場合には、故人の住所地の市区町村役場に「世帯主変更届」を提出します。
期限は14日以内とされていますが、市区町村役場に提出するものであるため、死亡届の提出と一緒に行うことをおすすめします。 -
(3)国民健康保険の資格喪失手続き
亡くなった方が国民健康保険に加入していた場合には、国民健康保険の資格喪失手続きが必要になります。
故人が世帯主である場合には、同じ世帯の家族についても国民健康保険証の書き換えが必要となりますので、故人の分に加え、家族の健康保険証も持参することになります。 -
(4)介護保険資格の資格喪失手続き
故人が40~64歳までの方で、医療保険に加入しており、要介護(要支援)認定を受けていた場合、または故人が65歳以上の方の場合には、介護保険資格の喪失手続きが必要になります。
その際には、介護保険被保険者証及び介護保険負担限度額認定証(交付を受けている場合)を返却する必要があります、 -
(5)公共料金などの名義変更・解約
亡くなった方が電気、ガス、水道などの公共料金の名義人であった場合には、そのままの状態だと、公共料金の引き落としができなかったり、同居の家族がいない場合などには無駄な料金が発生し続ける可能性があります。
名義変更や解約には特に期限は設けられていませんが、早めに対応することをお勧めします。
4、3か月以内にやるべきこと
被相続人が亡くなってから3か月以内にやるべき手続きとしては、以下のようなものがあります。
-
(1)相続人調査・相続財産調査
相続人調査とは、相続人が誰であるかを確定させるために行う調査です。
また、相続財産調査は、被相続人の相続財産を確定させるために行う調査です。
相続人調査および相続財産調査に期限は設けられていませんが、後述する相続放棄や限定承認の申述をするかどうかを判断するために必要な調査となりますので、3か月以内といわず早期に対応すべきです。 -
(2)相続放棄・限定承認の申述
被相続人に借金などの負債があった場合には、それも相続財産として遺産相続の対象になります。
借金などの負債の相続をしたくないという場合には、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄(相続を一切受けないようにする手続き)または限定承認(相続によって得たプラスの財産の額を限度として、マイナスの財産を相続する手続き)の申述を行う必要があります。
特別な事情がない限り、3か月の熟慮期間が経過してしまうと、相続を承認(単純承認)したものとみなされ、それ以降は相続放棄や限定承認を行うことができなくなることに注意してください。 -
(3)所得税の準確定申告
亡くなった方が自営業者や不動産所得がある方の場合には、所得税の準確定申告が必要になります。
通常の確定申告は翌年の2月16日~3月15日までの間に行いますが、準確定申告の期限は相続開始を知った日の翌日から4か月以内になるため、相続人の方は忘れずに手続きを行いましょう。
5、10か月以内やるべきこと
被相続人が亡くなってから10か月以内にやるべき手続きとしては、以下のようなものがあります。
-
(1)遺産分割協議
被相続人の遺産を分けるためには、相続人全員が参加して遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議自体には期限は設けられていませんが、上で述べた相続放棄・限定承認の議論や、次に述べる相続税の申告と納税など、相続に関する様々な期限がありますので、なるべく早期に対応することが望ましいです。相続税の負担を巡り、問題が生じないようにするためには、相続開始から10か月以内を目標に遺産分割協議を成立させることをお勧めします。 -
(2)相続税の申告と納税
遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合は、相続税の申告および納税が必要になります。基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算した金額です。
相続税の申告が遅れると、ペナルティーとして延滞税や加算税などが課されますので、期限内に申告および納税を行うことが大切です。
6、数年以内にやるべきこと
被相続人が亡くなってから数年以内にやるべき手続きとしては、以下のものがあります。
-
(1)遺留分侵害額請求
被相続人が遺言書を残していた場合には、遺言書の内容にしたがって遺産の分配を行います。
しかし、相続人には遺留分という最低限の遺産取得割合が保障されているため、遺言により自己の遺留分が侵害された場合には、遺留分侵害額請求権を行使して、侵害された遺留分相当額を取り戻すことが可能です。
このような遺留分侵害額請求は、相続の開始および遺留分の侵害を知ったときから1年以内に行使しなければなりません。なお、相続開始時から10年を経過した場合にも請求はできなくなりますので、ご注意ください。 -
(2)相続登記の申請
被相続人の遺産に不動産が含まれる場合には、被相続人名義から相続人名義に変更するための相続登記が必要になります。
法改正により令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化され期限が設けられることになりました。相続(遺言も含みます。)により不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければならず、正当な理由なく相続登記の申請をしなかった場合には、10万円以下の過料の対象になります。遺産分割により不動産を取得した場合には、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記が必要です。早期に遺産分割をすることが難しい場合には、新設された「相続人申告登記」を活用することが考えられます。
なお、令和6年4月1日以前に相続が開始している場合であっても、相続登記がなされていない場合には、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。 -
(3)死亡保険金の請求
亡くなった方が生命保険に加入していた場合、受取人に指定された方は、保険会社に対して死亡保険金を請求することができます。
死亡保険金は契約者が死亡すれば自動的に支払われるものではないため、受取人が請求する必要があります。
死亡保険金の請求期限は3年とされていますので、家族が亡くなった場合には、保険証券などを確認し、忘れずに保険金請求を行いましょう。 -
(4)遺族年金の請求
亡くなった方の配偶者や子どもは、遺族年金を受け取ることができる可能性があります。
遺族年金の請求期限は死亡した日から5年以内となっています。
請求をしなければ遺族年金の支給は開始されないので、まずは自身が遺族年金を請求することができるのか、年金事務所等に相談しましょう。
7、相続が発生したらまず弁護士に相談
遺産相続が発生した場合には、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
-
(1)必要な相続手続きをアドバイスしてもらえる
相続が発生すると、相続人は、さまざまな手続きを行わなければなりません。
相続手続きのなかには期限が設けられているものもあるため、自分に関係する手続きをしっかりと把握したうえで、スケジュールを立てていく必要があります。
しかし、遺産相続は多くの方にとって初めての経験となるため、何から手を付ければよいかわからないこと多いでしょう。
弁護士に相談することで、必要な相続手続きや期限などについてアドバイスを得られます。期限を超過してしまうとペナルティーが生じる可能性もあるため、早い段階から弁護士に相談して手続きを進めていきましょう。 -
(2)迅速かつ正確な相続財産調査が可能
被相続人に借金などがある場合には、3か月以内に相続するかどうかを判断する必要があります。
その判断をするためには、プラスの財産とマイナスの財産を正確に把握しなければなりません。
弁護士に依頼すれば、相続放棄や限定承認の判断に必要となる相続財産調査を迅速かつ正確に行うことができるため、相続放棄および限定承認の期限内に十分な判断資料をそろえることが可能になります。 -
(3)代理人として遺産分割協議に参加してもらえる
弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として遺産分割協議に参加することができます。
資産分割協議では、お互いの利害が対立することが多く、当事者同士の話し合いではどうしても感情的になってしまいがちです。
弁護士が介入することでお互いに冷静になって話し合いを進めることが可能になり、遺産分割協議も成立しやすくなるでしょう。
また、遺産分割協議に関して考慮しなければならない特別受益や寄与分などについても、弁護士に相談すれば法律の専門知識に基づいたアドバイスを受けることができます。
8、まとめ
相続が発生すると、さまざまな手続きが必要になります。
必要な手続きを漏れなく処理していくために、早い段階から、専門家である弁護士のアドバイスやサポートを受けましょう。
ベリーベスト法律事務所には、弁護士のほか、グループ内に税理士や司法書士も在籍しており、相続税の申告や相続登記が必要な事案など幅広いご相談に対応可能です。相続が発生したが、やることがわからずお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 浦和オフィスまで、お気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています