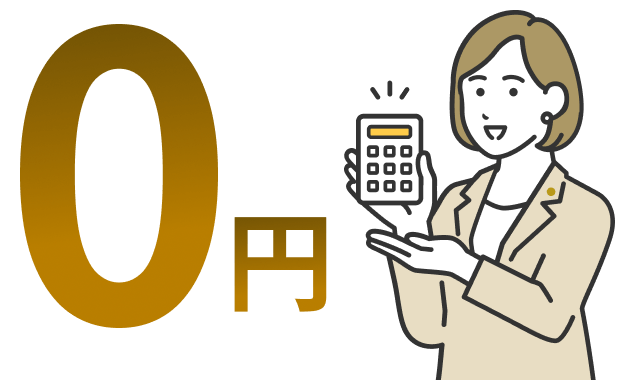代表相続人とは? 勝手に相続手続きを進められた場合の対処法
- 遺産を受け取る方
- 代表相続人
- 勝手に

令和4年のさいたま市浦和区の死亡者数は1388名でした。被相続人が亡くなり、相続を進める際には「代表相続人(相続代表者)」が重要になります。
代表相続人とは、すべての相続人を代表して相続手続きを進める人で、相続手続きがスムーズにいくよう取り仕切る役を担っています。しかし、代表相続人が勝手に相続手続きを進めてしまい、トラブルに発展するケースも少なくありません。
本記事では、代表相続人の役割とともに、代表相続人が勝手に相続手続きを進めてしまった場合の対処法などを、ベリーベスト法律事務所 浦和オフィスの弁護士が解説します。


1、代表相続人とは?
「代表相続人」とは、複数いる相続人の代表者です。遺産相続に関する手続きを進めるに当たり、代表相続人は相続人全員のまとめ役として行動することが求められます。
-
(1)代表相続人の役割
代表相続人の役割は、相続権を有する人(相続人)全員の意見や資料などを集約し、相続手続きを円滑に進めることです。
相続手続きの中には、相続人全員が共同で対応すべきものが含まれています。このような手続きを円滑に進めるためには、代表相続人のまとめ役としての役割が重要になります。 -
(2)代表相続人を定めた方がいいケース
相続人が複数いる場合に、代表相続人を定めた方がスムーズなケースとしては、以下の例が挙げられます。
- 遺産分割または遺言書の内容に従い、被相続人口座の預貯金の払い戻しを受ける場合
- 被相続人が所有していた不動産について、固定資産税の納税通知書を受け取る場合
- 遺産分割の内容に従い、不動産の相続登記を申請する場合(特に共有状態で登記をする場合や、換価して分割する場合等)
- 相続税の申告をする場合
2、代表相続人が勝手に相続手続きを進めている場合は、弁護士に相談を
代表相続人であっても、相続手続きの進め方を勝手に決めてよいわけではありません。相続手続きを進めるに当たっては、各相続人の同意を得る必要があります。
代表相続人が勝手に相続手続きを進めてしまっている場合に、弁護士が行うサポートや手続きの流れを解説します。
-
(1)代表相続人の独断専行を阻止するため、弁護士ができるサポート
弁護士は、代表相続人の独断専行を阻止するため、代表相続人とよく話し合います。
代表相続人はまとめ役に過ぎず、勝手に相続手続きを進める権限はないことを十分に説明し、適切に相続手続きが進められるように取り計らいます。
代表相続人が独断専行をやめない場合は、必要に応じて裁判手続きを活用します。弁護士は裁判手続きに精通しているため、あらゆる手段を用いて代表相続人の勝手な行動を阻止します。 -
(2)弁護士に相談する際に、持参するとよい資料(証拠)
代表相続人の勝手な行動について弁護士に相談する際には、どのような行動について困っているのかが分かる資料を持参すると、スムーズに状況を理解してもらうことができます。
状況に応じて、以下のような資料を持参するとよいでしょう。被害の状況 持参する資料 不動産を勝手に処分された 不動産売買契約書、登記事項証明書など 預貯金を勝手に引き出された 通帳、入出金明細など 株式などの有価証券を勝手に売却された 証券口座の取引記録など 相続放棄の手続きを勝手にされた 相続放棄申述受理通知書、相続放棄申述受理証明書など
お問い合わせください。
3、弁護士を通じた相続トラブルの解決の流れ
代表相続人の勝手な行動で発生した相続トラブルは、以下の手続きによって解決を目指します。いずれの手続きについても、弁護士に依頼すれば全面的にサポートしてもらえます。
-
(1)当事者間での協議
まずは、代表相続人を含む相続人の間で協議を行い、解決策を話し合います。
代表相続人に対しては、直ちに勝手な行動をやめ、遺産などを元の状況に戻してもらうよう説得しましょう。完全な原状回復が難しい場合には、金銭による補填などの代替措置も検討すべきです。
弁護士は、各相続人の意向や遺産の状況などを踏まえた上で、円満にトラブルを解決できる方法を模索します。代表相続人に対する説明や説得も、弁護士が率先して行います。 -
(2)遺産分割調停・民事調停
協議によってトラブルが解決できないときは、裁判所における調停へと場を移すことも選択肢の一つです。
遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てましょう。預貯金の使い込みなど、遺産分割以外の問題が発生しているときは、簡易裁判所の民事調停も利用することができますし、相手が協議に応じるのであれば、事実上遺産分割調停の中で話し合うことも可能です。
調停では、中立の調停委員が当事者の主張を公平に聴き取り、歩み寄りを促しつつ合意形成をサポートします。
弁護士は調停期日に同席し、依頼者の主張を調停委員に対して分かりやすく伝えます。弁護士を通じて説得的な主張をすれば、調停委員を味方に付けやすくなるでしょう。
当事者の合意が得られたら、その内容を記載した調停調書が作成され、調停成立となります。 -
(3)審判・訴訟
調停は話し合いによって合意を目指す手続きですが、当事者の主張が大きく食い違っていると、合意が得られないケースもあります。その場合は、裁判所の判断によって強制的に解決を図ることを考えましょう。
遺産分割調停が不成立となった場合は、家庭裁判所が審判によって遺産分割の内容を決定します。
民事調停が不成立となった場合は、裁判所に対して別途訴訟を提起しましょう。訴訟では、当事者の主張・立証を踏まえた上で、裁判所が判決によって結論を示します。
審判や訴訟では、当事者の主張や提出した証拠などに基づき、裁判所が客観的な立場から判断を行います。
弁護士は依頼者の代理人として、法的根拠に基づく主張を行い、その主張を補強する証拠資料を提出するなどして、依頼者にとって有利な解決を得られるように尽力します。
審判や判決が確定した場合、その内容は当事者を拘束します。代表相続人などが審判や判決で確定した義務を履行しない場合は、裁判所に強制執行を申し立てることができます。
4、【ケース別】代表相続人が勝手に相続手続きを進めてしまった場合の対処法
代表相続人の独断専行によって発生しがちな相続トラブルのパターンごとに、問題解決の方法を紹介します。具体的にとるべき対応は、状況によって異なるため、早めに弁護士にご相談ください。
-
(1)不動産を勝手に処分された場合
代表相続人が、他の相続人の委任状や遺産分割協議書を偽造したり、実印や印鑑登録証明書を流用したりして、相続財産である不動産を勝手に売却してしまうケースがあります。
本人(=代表相続人以外の相続人)の同意を得ない不動産の売却は無権代理行為と呼ばれ、原則として、本人が後から認めなければ、本人に対してその効果を生じません(民法第113条第1項)。そのため、不動産の買主に対して不動産の返還を請求しましょう。
ただし、買主が、代表相続人が本人を代理することができると信じたことに正当な理由があるときは、代表相続人による売却が有効と判断されてしまうことがあるので注意が必要です(民法第110条)。
買主から不動産を取り戻すのが難しい場合には、売却代金にあたる金額を遺産の中に戻すよう代表相続人に対して請求しましょう。 -
(2)預貯金を勝手に引き出された場合
共同相続人は、単独で引き出すことができる一定の額(民法第909条の2)を除き、相続財産である預貯金を勝手に引き出すことはできません。これは代表相続人であっても同様です。
代表相続人による預貯金の無断引き出しは、通帳や入出金明細を確認することで判明することがあります。預貯金の無断引き出しが判明した場合は、代表相続人に対して同額の返還を請求しましょう。 -
(3)株式などの有価証券を勝手に売却された場合
亡くなった被相続人が保有していた株式などの有価証券は、遺産分割協議や遺言書の内容に従って分けるべきものです。代表相続人には、相続財産である有価証券を勝手に売却する権限はありません。
被相続人が亡くなった後に有価証券が売却されている場合は、代表相続人等が勝手に売却した可能性が高いため、速やかに証券会社へ連絡し、相続手続きが完了するまで取引を停止してもらいましょう。
その上で、その売却した有価証券の代金にあたる額が証券口座に残っていれば、その金額を相続人間で分けることになります。代表相続人がすでに出金してしまっている場合は、売却代金相当額の返還を請求しましょう。 -
(4)相続放棄の手続きを勝手にされた場合
相続放棄は、各相続人が自分の意思に基づき、単独で行うべきものであって、代表相続人が勝手に手続きを行うことは許されません。
家庭裁判所が受理の審判を行う前であれば、家庭裁判所に「取下書(取り下げの申し出)」を提出して、相続放棄の申述を取り下げることができます(家事事件手続法第82条第1項)。
すでに相続放棄の申述が受理されてしまった場合は、家庭裁判所に対して相続放棄を取り消す旨を申述しましょう(民法第919条第2項、第4項)。
5、まとめ
代表相続人は、相続人全員を代表して相続手続きを進める役割を担います。そのため、責任感があり、時間的に余裕がある人を代表相続人に選ぶとよいでしょう。
代表相続人が勝手に相続手続きを進めてしまい困っている方は、弁護士に相談しましょう。早期に弁護士へ相談すれば、トラブルの深刻化を防ぐことができます。
ベリーベスト法律事務所は、相続トラブルに関するご相談を随時受け付けております。代表相続人の勝手な行為について悩んでいる方は、ベリーベスト法律事務所 浦和オフィスへご相談ください。
お問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています