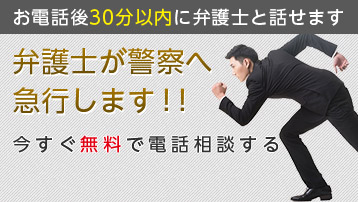逮捕後の勾留期間|刑事手続きの流れや勾留を回避する方法
- その他
- 逮捕後
- 勾留

埼玉県警察が公表している犯罪統計によると、令和6年中に埼玉県内で認知された刑法犯の総数は5万1667件で、そのうち検挙された事件は1万6691件でした。検挙率でいうと32.3%となっています。
何らかの犯罪を起こして逮捕されると身柄拘束をされてしまいます。このような逮捕後の勾留による身柄拘束を回避する方法はあるのでしょうか。
今回は、逮捕後の勾留期間や勾留を回避する方法などについて、ベリーベスト法律事務所 浦和オフィスの弁護士が解説します。


1、逮捕後の勾留期間と刑事手続きの流れ
逮捕後、勾留請求が認められると、原則10日間、最大20日間の勾留が行われることになります。以下では、逮捕後の勾留期間と刑事手続きの流れについて説明します。
-
(1)逮捕・検察へ送致:逮捕後48時間以内
警察により逮捕されると警察署に連行され、警察署内の留置施設で身柄拘束されます。
逮捕中は警察による取り調べを受けることになり、その間は家族や友人との面会は一切できません。
警察による逮捕には48時間という時間制限があるため、警察は、被疑者を釈放しない場合は逮捕から48時間以内に被疑者の身柄を検察官に送致しなければなりません。 -
(2)勾留請求:送致後24時間以内
検察官は、被疑者に対する取り調べを行い、被疑者の身柄拘束を継続するかどうかを検討します。その結果、引き続き身柄拘束をする必要があるとの判断に至ったときは、送致から24時間以内で、かつ逮捕から72時間以内に裁判官に対して勾留請求を行います。
-
(3)勾留・起訴の決定:最大20日間
裁判官は、被疑者に対する勾留質問を行い、被疑者の言い分や捜査関係資料などを確認した上で、勾留を許可するか却下するかの判断を行います。
令和5年(2023年)の検察統計によると刑法犯全体の勾留請求件数は6万7240件あり、そのうち勾留が許可された件数は6万4683件となっています。勾留率でいうと約96.2%ですので、勾留請求された事件のほとんどが勾留されていることがわかります。
勾留が許可されるとその勾留期間は原則として10日間ですが、勾留延長が許可されるとさらに最長10日間の勾留期間が追加されます。そのため、勾留期間は最長で20日間となります。 -
(4)刑事裁判
検察官は、勾留期間が終了する前に事件を起訴するか不起訴にするかの決定をします。
日本の刑事司法では、起訴されてしまうと99%以上の割合で有罪になってしまいますので、前科を回避するためには不起訴処分を獲得することが重要になります。
不起訴処分になれば前科が付くこともなく、その時点で釈放となります。
2、起訴後の勾留期間と保釈請求について
勾留されている被疑者が起訴されると身柄拘束はどうなるのでしょうか。以下では、起訴後の勾留と保釈請求について説明します。
-
(1)起訴後の勾留期間
検察官は、起訴後も以下のような要件に該当する場合には、裁判所に勾留を求めることができます。
- 被告人が定まった住居を有しない
- 被告人が証拠を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある
- 被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある
起訴前の勾留を「被疑者勾留」と呼ばれるのに対して、起訴後の勾留は「被告人勾留」と呼ばれます。
実務では、裁判への出廷を確保し、被害者に脅迫や危害を加えるのを避ける目的で、起訴後は被告人勾留に切り替わるケースがほとんどです。すなわち、勾留された被疑者が起訴されると、そのまま身柄拘束が継続する可能性が高いということです。
起訴後の被告人勾留は、勾留期間が原則として起訴日から2か月ですが、一定の場合には1か月ごとに更新が認められています。要件を満たす限り、更新回数には制限がありませんので、そのままの状態だと刑事裁判が終わるまで身柄拘束が継続することになります。 -
(2)保釈請求について
起訴後の被告人勾留は、被疑者勾留のような延長回数の制限がないため、実質的には無期限の勾留期間になってしまいます。しかし、起訴後であれば保釈請求が可能になりますので、保釈請求が認められれば、一時的に釈放してもらうことができます。
以下では、保釈制度の概要や条件などを説明します。
① 保釈制度の目的・概要
保釈制度とは、裁判所に保釈保証金を納付することで被告人の身柄を一時的に解放してもらえる制度です。
被告人勾留が行われると、裁判が終わるまでの数か月から数年間は、身柄拘束された状態が続きますので、そのままでは仕事を解雇され生活基盤を失うなどして、社会復帰が困難な状態になってしまいます。
刑事裁判では、「推定無罪の原則」が働き、有罪が確定するまではあくまでも無罪の立場で扱われるべきとされています。そのため、刑罰が確定していない段階で長期間にわたる身柄拘束をし続けるのは、本来避けるべき事態です。
そこで、被告人の不利益を少しでも軽減するために、裁判に確実に出頭することを条件として、暫定的に身柄を解放しようとする制度が保釈制度になります。
② いつから保釈請求できるのか
保釈請求は、起訴後であればいつでも行うことができます。
他方、被疑者勾留には、保釈制度は存在しませんので、被疑者として逮捕・勾留中には、保釈請求を行うことはできません。
③ 保釈申請が許可されるための条件
保釈には、「権利保釈」「裁量保釈」「義務的保釈」があります。以下では、それぞれの保釈が許可されるための条件を説明します。- 権利保釈:権利保釈とは、法律上の除外事由が存在しなければ必ず認められる保釈をいいます。 具体的には、以下の6つの除外事由のいずれにも該当しなければ保釈が許可されます。
- 裁量保釈:裁量保釈とは、権利保釈が認められない場合でも裁判所の職権により保釈が許可される制度をいいます。裁量保釈は、犯罪の軽重、身元引受人の有無、前科前歴の有無などさまざまな事情を考慮して判断しますので、権利保釈のように明確な条件があるわけではありません。
- 義務的保釈:義務的保釈とは、勾留期間が不当に長くなった場合に請求または職権により保釈が許可される制度です。しかし、実務上義務的保釈が認められるケースはほとんどありません。
① 重大犯罪であること:死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪
② 重大犯罪の前科があること:死刑または無期もしくは長期10年を超える懲役もしくは禁錮にあたる罪で有罪の宣告を受けた
③ 常習犯であること:常習として長期3年以上の懲役または禁錮にあたる罪を犯した
④ 証拠隠滅のおそれ等があること:罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある
⑤ 被害者や証人などに危害を加えるおそれがあること:被害者や証人その親族の身体・財産に対し危害を加えまたは畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がある
⑥ 被告人の氏名または住居がわからないこと:友人宅やホテルを泊まり歩くなど定まった住居地がない
お問い合わせください。
3、逮捕後、長期間の勾留を回避するには?
逮捕後、長期間の勾留を回避するにはどうしたらよいのでしょうか。以下では、長期間の勾留を回避するための対処法を説明します。
-
(1)検察官の勾留請求を阻止する
検察官による勾留請求を阻止することができれば、勾留されることはありません。
勾留請求を阻止するには、検察官に「勾留請求に対する意見書」を提出し、その中で勾留の要件を満たさないことを主張していく必要があります。また、意見書の提出だけではなく、検察官と電話面談をして検察官を説得することも有効な手段です。
なお、令和5年(2023年)の検察統計によると逮捕され検察に送致された刑法犯の総数(検察庁逮捕含む)は7万1607件あり、そのうち勾留請求されたのは6万7240件でしたので、勾留請求率は約94%となります。 -
(2)裁判官の勾留決定を阻止する
検察官に勾留請求されたとしても、裁判官の勾留決定を阻止することができれば、勾留されることはありません。
裁判官の勾留決定を阻止するには、裁判官に対して「勾留請求の却下に対する意見書」する、裁判官と電話面談をする、裁判官と直接面談をするなどして、勾留要件を満たさないことを説得していく必要があります。
なお、令和5年(2023年)の検察統計によると刑法犯全体の勾留請求件数は6万7240件あり、そのうち勾留が許可された件数は6万4683件でしたので、勾留率は約96.2%となります。 -
(3)勾留中に準抗告を申し立てる
裁判官により勾留決定されてしまったときは、準抗告をしてそれが認められれば身柄を解放してもらうことができます。
勾留に対する準抗告とは、裁判官の勾留決定に対する不服申し立ての手続きで、勾留決定が勾留の要件を満たしていないという理由で勾留の破棄を求めるものになります。
準抗告は、簡単には認められませんが、準抗告をすることでその後の勾留延長に対して慎重な判断を促す効果も期待できます。 -
(4)勾留延長を阻止する
勾留延長が認められてしまうと勾留期間が最長10日間延長となりますので、勾留延長を阻止できれば長期間の勾留を回避することができます。
勾留延長を阻止するには、検察官に対して勾留延長請求をしないよう働きかける方法や裁判官に対して勾留延長決定をしないよう働きかける方法があります。いずれにしても勾留請求の要件である「やむを得ない事由」がないことを説得的に主張していくことが重要です。
4、逮捕されたらまずは弁護士に相談を
家族や恋人が犯罪を起こして逮捕されてしまったときは、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
-
(1)逮捕後すぐに接見してアドバイスを受けられる
逮捕中は家族や恋人であっても面会することができません。逮捕後72時間以内に面会できるのは、弁護士だけです。
不安な気持ちを少しでも和らげるためにも、すぐに弁護士に依頼して本人との面会をしてもらうようにしましょう。弁護士が面会して今後の刑事事件の流れや処分の見通し、早期釈放に向けた対処法などを伝えることで、不安な気持ちもある程度は解消されるはずです。
なお、家族や本人からの伝言は弁護士を通じて伝えることができます。 -
(2)取り調べで不利な供述調書を作成される事態を防げる
逮捕後は捜査機関による取り調べが行われ、被疑者の供述内容をまとめた供述調書が作成されます。
供述調書は、十分に内容を確認することなく署名・押印をしてしまうと、その後の裁判で不利な証拠になってしまうおそれがあります。一度署名・押印した調書は、後から訂正することは困難ですので、取り調べには慎重に対応しなければなりません。
逮捕後すぐに弁護士に依頼して面会できれば、弁護士から取り調べに対する基本的な対応方法や黙秘権の行使などのアドバイスを受けることができますので、不利な供述調書を作成されるリスクを回避できます。 -
(3)身柄拘束の長期化を防ぎ早期釈放を目指せる
逮捕後勾留されると、最長で23日間身柄を拘束されてしまいます。また、起訴されてしまえば被告人勾留に切り替わり実質的に無制限の身柄拘束を受けることになります。身柄拘束期間が長くなればなるほど本人の心身の負担も大きくなるため、早期の身柄解放を実現することが重要です。
弁護士に依頼すれば、捜査段階であれば勾留請求・決定の阻止、勾留に対する準抗告などの手段で早期の身柄解放を目指すことができ、起訴後であれば保釈請求により身柄解放の実現を目指します。
早期の身柄解放を目指すには、刑事事件の実績が豊富な弁護士のサポートが重要です。早めに弁護士に相談することをおすすめします。
5、まとめ
逮捕後、勾留請求が認められると、原則10日間、最大20日間の勾留が行われることになります。勾留期間が長くなると仕事を解雇されて、生活基盤を失うリスクがありますので、早期の身柄解放を実現することが重要です。
早期の身柄開放には刑事事件の経験豊富な弁護士のサポートが大切です。家族や恋人が逮捕されてしまったときはベリーベスト法律事務所 浦和オフィスまでご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています