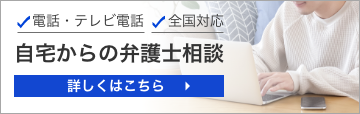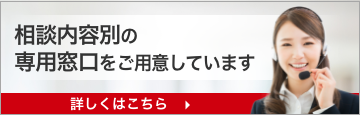病気を理由に解雇できるケース|解雇手続きの進め方や注意点
- 労働問題
- 解雇理由
- 病気
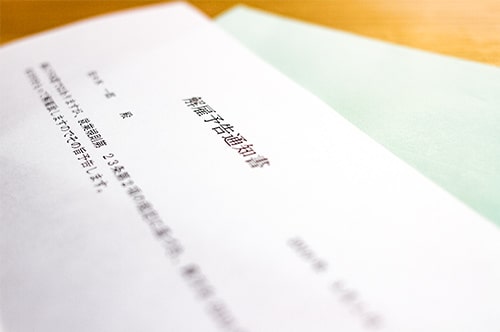
令和5年度に埼玉県内の総合労働相談コーナーに寄せられた民事上の個別労働紛争は延べ9638件で、そのうち1120件(11.6%)が解雇に関するものでした。
病気で長期間休んでいる従業員(労働者)は、解雇できる場合とできない場合があります。法律や就業規則を確認した上で、できる限りトラブルを防げるように対応しましょう。
本記事では、病気を理由に従業員を解雇できるケースとできないケース、従業員が病気になった場合の対処法や注意点などを、ベリーベスト法律事務所 浦和オフィスの弁護士が解説します。
出典:「『令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況(埼玉労働局)』を公表します」(埼玉労働局)
1、病気を理由に従業員を解雇できるケース
病気やケガを理由に解雇する場合はまず、その原因が業務によるもの(業務災害)なのか、業務と関係なく生じた病気やケガ(私傷病)なのかで対応が変わります。
業務災害による病気やケガの場合には、厳格な法定の解雇制限がありますが、私傷病の場合はそれがありません。会社は以下の条件を満たせば従業員の解雇が可能になります。
- (例)
- 就業規則の解雇事由に「業務外の傷病により業務に耐えられないとき」という規定があり、かつ、就業規則の私傷病休職の要件を充たさないこと
- 就業規則の私傷病休職の要件を充たす場合で就業規則に定められた休職期間が満了すること
② 解雇をする客観的・合理的な理由があり、かつ解雇が社会通念上相当と認められること
- (例)
- 復職の見込みがないと判断されること
- 配置転換などの解雇回避措置を検討していること
したがって、病気になった従業員を解雇するためには、労働契約または就業規則において「従業員が業務に耐えられない程度の傷病になった場合は解雇できる」と定められていることが最低限必要です。ただし、この場合でも就業規則に定められた私傷病休職要件を充たす場合は休職を命じなければならず、いきなり解雇とすることはできません。
また、休職期間の満了時に十分に働ける状態での復職が不可能と判断される場合や、配置転換などの解雇回避措置をしても復職が不可能だった場合など、解雇がやむを得ないと言えるだけの事情が存在することが求められます。
2、病気を理由に従業員を解雇できないケース
以下に挙げるようなケースでは、病気を理由に従業員を解雇することができません。
-
(1)業務災害の場合
業務上の原因によって病気にかかった(=業務災害に遭った)従業員については、療養のために休業する期間およびその後30日間は、原則として解雇することが禁止されています(労働基準法第19条第1項本文)。
ただし例外的に、以下の場合には業務災害に遭った従業員を解雇することが認められる可能性が高いと考えられます。- 療養開始後3年を経過しても病気が治らないときに、平均賃金の1200日分の打切補償(長期にわたる療養補償を打ち切る代わりに支給される補償金)を支払う場合(労働基準法第81条)
- 天災地変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり、当該事由について労働基準監督署長の認定を受けた場合(労働基準法第19条第1項但し書き)
なお、打切補償については、支払えば自動的に解雇できるわけではありません。解雇の正当性は客観的に合理的な理由や社会通念上の相当性があるかどうか別途判断される必要があります。
- 療養開始後3年を経過しても病気が治らないときに、平均賃金の1200日分の打切補償(長期にわたる療養補償を打ち切る代わりに支給される補償金)を支払う場合(労働基準法第81条)
-
(2)社内規程で認められた条件で休職している場合
病気になった原因が会社の業務ではなくても、会社に休職の規定が設けられており、その制度を利用して休職している従業員については、休職期間中の解雇が認められる可能性は低いと考えられます。
休職制度を利用することは、労働契約に基づく従業員の権利であるため、休職中の従業員を解雇することは社会通念上不相当と思われるためです。
休職制度を利用している従業員を解雇するためには、少なくとも制度上の休職期間満了を待たなければなりません。 -
(3)解雇権の濫用に当たる場合
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、解雇権の濫用により無効です(労働契約法第16条)。
たとえば、「従業員が病気になったこと」が解雇事由に挙げられていても、軽症なのに解雇することは不合理と考えられます。
極端な例ですが、数日で治る風邪にかかっただけで解雇することは認められません。このような解雇は、解雇権の濫用として無効となります。
病気を理由に従業員を解雇するためには、その病気が重症であり、復職に重大な支障が生じていることが必要で、かつ、私傷病による休職制度がある場合は休職期間の満了が必要です。
3、従業員が病気になった場合の対処法と注意点
従業員が病気になり長期的に休む状況となった場合には、会社は段階を踏んで以下の対応を行いましょう。
-
(1)診断書を提出させ、病気の症状や原因を正確に把握する
まずは、従業員に対して診断書の提出を求めましょう。病気の症状や原因を正確に把握するためです。
病気の症状がどの程度か、原因が何であるかによって、会社としてとるべき対応が変わります。従業員の自己申告を信頼するのではなく、必ず医師の診断書の提出を求めましょう。
ただし、従業員のプライバシーに配慮し、必要以上の情報を求めないよう注意する必要があります。 -
(2)休職や解雇などについて、法令や就業規則を確認する
就業規則に休職の規定がある場合は、従業員が病気で長期の療養が必要になった際、まずはその従業員を休職させることになります。
病気で休んでいる従業員に対しては、原則として賃金を支払う必要はありません。
ただし、会社が社内規定で休職制度を設けており、休職中も賃金が発生すると定められている場合は、その定めに従って賃金を支払う必要があります。
また、病気の従業員を解雇するためには、労働契約または就業規則において、従業員の病気が解雇事由に掲げられていなければなりません。
上記のことを踏まえた上で、賃金の支払いや解雇などについて、法令や就業規則を確認しましょう。安易な対応をしてしまうと、従業員との間で深刻なトラブルが生じるおそれがあるので注意が必要です。 -
(3)復職の見通しを確認する
病気になった従業員が比較的短期間で復職できるようであれば、退職を求めるのではなく、復職に向けた環境を整えるべきです。
しかし、就業規則で定められた休職期間内に復帰することが難しいことが明白であるケースなど、従業員の療養が長引くようであれば、退職勧奨や解雇を検討することもやむを得ないでしょう。
復職の見通しについては、医師の診断書を確認すればある程度わかりますが、従業員本人から話を聞くことも重要です。本人と直接話をすれば、病気の状態をより明確に確認でき、復職の見通しについても判断しやすくなります。 -
(4)解雇する前に、退職勧奨をする
病気療養が長引いている従業員を退職させたい場合は、いきなり解雇するのではなく、その前に退職勧奨を行いましょう。
退職勧奨とは、会社から従業員に対して退職を勧めることです。従業員が退職勧奨を受け入れた場合は、合意退職となります。
合意退職は、解雇ではないので厳しい法的規制がかかりません。そのため、後から従業員との間で法的紛争が生じるリスクを軽減できます。
ただ、退職勧奨は、あくまでも任意の退職を求める形で行わなければなりません。退職勧奨が強制に及ぶ場合は、実質的な解雇であると判断され、厳格な解雇規制が適用されてしまいます。
特に、以下のような形で退職勧奨を行うと、退職強要(=実質的な解雇)と判断される可能性が高いのでご注意ください。退職強要の例 - 退職勧奨に応じなければ解雇すると告げた
- 従業員を密室に閉じ込めて、複数人で退職を求めた
- モチベーションを失わせて退職に追い込むため、全く仕事がない部署へ異動させた
退職金の上乗せなど、従業員にとって有利な条件を提示すると、退職勧奨に応じてもらえる可能性が高まります。従業員の説得が難航している場合は、選択肢の1つとして検討しましょう。
-
(5)解雇する場合は、要件を慎重に検討する
重病の従業員が退職勧奨に応じない場合は、解雇を検討することもやむを得ないでしょう。
ただし解雇を行う際は、法令や就業規則に基づいて慎重な判断が必要です。
以下の項目についてしっかり確認しましょう。- ① 解雇の法的要件に該当するかどうか
従業員の解雇には労働契約や就業規則で定められた解雇事由に該当することと、労働契約法における解雇権の濫用に当たらないことが必要です。
従業員の病気が解雇事由に該当する場合に限り、病気の従業員の解雇を検討することができます。
- ② 解雇の妥当性があるかどうか
病気の症状・療養期間の長さ・回復の見込み・従事する業務の内容などを総合的に考慮して、解雇の客観的合理性と社会的相当性が認められるかどうかも検討しなければなりません。
たとえば、職種や職務を限定しない雇用契約の場合は、職種の変更や配置転換を試みるなど、従業員が復職するために、会社側は最大限努力する必要があります。
復職が十分期待できるのに解雇したり、病気になってから短期間で解雇したりすることは、解雇権の濫用として無効と判断される可能性が高いです。
従業員を安易に解雇すると、不当解雇を主張されてトラブルに発展するおそれがあります。弁護士のアドバイスを受けつつ、本当に解雇してよいかどうかを慎重に検討しましょう。 - ① 解雇の法的要件に該当するかどうか
-
(6)解雇の手続きを遵守する
実際に病気の従業員を解雇する場合は、解雇に関する法律上の手続きを遵守する必要があります。
具体的には、30日以上前に解雇を予告するか、または解雇予告手当を支払うことが必要です(労働基準法第20条)。
また、従業員から解雇理由証明書の交付を請求された場合は、遅滞なく交付しなければなりません(労働基準法第22条)。
解雇手続きに違反があると、従業員とのトラブルに発展するリスクが高まります。弁護士のサポートを受けながら、解雇手続きを適切に進めましょう。
4、解雇などの労働トラブルは弁護士に相談を
解雇を含めた人事・労務に関するトラブルは、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、労働トラブルのリスクからクライアント企業を守るため、主に以下のサポートを行っています。
- 労働契約のひな形や就業規則の整備
- 退職勧奨の方法に関するアドバイス
- 解雇の可否や手続きに関するアドバイス
- 従業員との代理交渉
- 労働審判の申し立て
- 訴訟の提起
従業員との労働トラブルにお困りの場合は、早い段階で弁護士にご相談いただき、共にスムーズな解決を目指しましょう。
お問い合わせください。
5、まとめ
病気を理由に従業員を解雇しようとする場合は、事前に法律や就業規則を確認し、慎重な検討を行うべきです。
弁護士のアドバイスを踏まえて、できる限りトラブルを防ぐことができるように対応しましょう。
ベリーベスト法律事務所は、従業員の解雇や、その他の人事・労務管理に関する企業のご相談を随時受け付けております。従業員が重大な病気にかかり、解雇してよいかどうか悩んでいる場合は、ベリーベスト法律事務所 浦和オフィスへぜひご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています